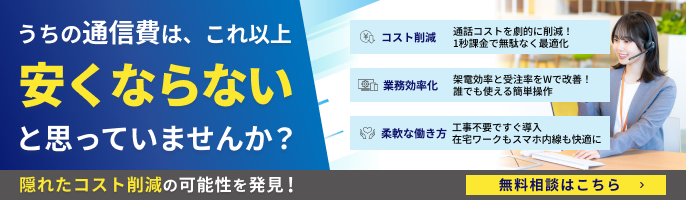2025/08/18
ビジネスフォンの価格はなぜ高い?総額がわかる費用内訳とコスト削減の方法を解説
ビジネスフォンの導入や入れ替えを検討する際、多くの担当者がその価格の複雑さに直面します。「電話機1台あたりの価格」で予算を組んだら、最終的な見積もりが想定を大幅に上回った、という経験はありませんか?
なぜなら、ビジネスフォンの総コストは機器代だけでなく、設置工事費や運用費など複数の要素から成り立っているからです。
このような課題を解決するため、本記事では法人向け電話ソリューションを専門とする株式会社ドリームソリューションが、ビジネスフォン価格の全貌を徹底解説します。初期費用から運用費用の内訳、新品・中古・リースの比較、そして「クラウドPBX」との違いまで、この記事を読めば、自社に最適な電話システムを選ぶための「考え方」が身につきます。
ビジネスフォン価格の全体像:初期費用と運用費用のすべて
ビジネスフォン導入で最も重要なのは、「トータルでいくらかかるのか(総所有コスト)」を正確に知ることです。ここでは、導入時に一度だけ発生する「初期費用」と、継続的にかかる「運用費用(ランニングコスト)」に分けて、全ての費用項目を解説します。
初期費用:最初にいくらかかる?
システムを稼働させるために最初に必要となる投資です。導入規模によって大きく変動し、総コストの大部分を占めることも多いため、正確な見積もりが欠かせません。
機器代金
- 主装置(PBX): 外線と内線をコントロールするシステムの「頭脳」です。新品の価格相場は20万円から100万円以上と、企業の規模が大きくなるほど高額になります。
- 電話機(多機能電話機): 従業員が実際に使う電話機本体の費用です。新品の場合、1台あたりの価格相場は15,000円から50,000円程度です。
工事費
- 基本工事費・派遣費: 技術者の派遣にかかる基本的な費用で、1回あたり7,000円から13,000円程度が目安です。
- 配線工事費: 主装置から各電話機までケーブルを配線する作業費用です。
- 電話機設置・設定費: 各電話機を設置し、内線番号などを設定する費用で、1台あたり9,000円から10,000円程度が相場です。
運用費用:月々いくらかかる?
システムの運用を続けるために、毎月または毎年発生する費用です。
- 回線利用料: NTTなどの通信キャリアに支払う電話回線の基本料金です。
- 保守費用: 故障時の修理や定期メンテナンスのための契約費用です。自社に機器を置く従来型の場合は加入が強く推奨されます。
【導入方法別】価格比較:新品・中古・リースのメリット・デメリット
ビジネスフォンの機器を手に入れる方法は、大きく分けて3つあります。まず、それぞれのポイントを比較表で確認しましょう。
導入方法別 比較早見表
| 比較項目 | 新品購入 | 中古購入 | リース契約 |
| 初期費用 | 最も高額。一括払い。 | 最も低額。大幅削減可能。 | 原則不要。月々払いに平準化。 |
| 総支払額 | 最も安価。 | 修理費次第で変動。 | 最も高額。手数料が上乗せ。 |
| 保証 | 充実したメーカー保証。 | 販売店の独自保証のみ。 | リース会社の動産保険適用が多い。 |
| 経理処理 | 資産計上(減価償却)。 | 資産計上(減価償却)。 | 全額経費として処理。 |
| 最新機能 | 利用可能。 | モデルによる(望めない)。 | 利用可能。 |
| 契約の縛り | なし。 | なし。 | あり(通常5〜7年)。中途解約不可。 |
| 推奨企業 | 資本に余裕がある企業。 | コスト最優先の企業。 | スタートアップなどキャッシュフロー重視の企業。 |
それぞれの方法について、詳しく解説します。
新品購入
メーカーや代理店から、全く新しい未使用の機器一式を購入する方法です。
- メリット: 充実したメーカー保証による長期的な安心感と、最新機能が利用できる点が魅力です。会社の資産として計上できます。
- デメリット: 導入時にまとまった資金が必要となり、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。
中古購入
他の企業で使われていた機器を、専門業者が整備して再販するものを購入する方法です。
- メリット: 新品に比べて初期投資を劇的に削減できるのが最大の魅力です。
- デメリット: メーカー保証がなく、故障時の修理はすべて実費です。古いモデルは修理部品が手に入らないリスクもあります。
リース契約
リース会社が新品の機器を購入し、企業は月額料金を支払って長期間レンタルする方法です。
- メリット: 初期投資が不要で、月々の支払いを経費として処理できます。スタートアップなどに最適です。
- デメリット: リース手数料が上乗せされるため支払総額は高くなり、原則として中途解約はできません。
価格を左右する2大選択肢:従来型ビジネスフォン vs. クラウドPBX
ビジネスフォンの価格と機能を決める最も根本的な選択は、システムの基盤を「従来型」にするか「クラウド型」にするかです。
- 従来型ビジネスフォン(社内に機器を置くタイプ): オフィスに「主装置(PBX)」という箱型の交換機を設置します。物理的な「製品」を購入し、自社で所有・管理する考え方です。
- クラウドPBX(インターネットを利用するタイプ): 物理的な主装置は設置せず、インターネット経由で機能を利用します。月額利用料を支払って電話交換「サービス」を利用する考え方です。
この「製品購入」か「サービス利用」か、という根本的な違いが、今後の価格や機能のすべてに関わってきます。
従来型ビジネスフォンの価格と選び方
自社内に設備を持つことによる安定性を重視する企業にとって、従来型ビジネスフォンは今も有力な選択肢です。
主要メーカーの特徴
- NTT: 国内シェア約50%のトップブランド。知名度と信頼性は抜群です。
- NEC: 大規模オフィスやコールセンター向けのシステムで高い評価を得ています。
- SAXA(サクサ): 中小企業市場で絶大な人気を誇り、コンパクトな製品が特徴です。
事業規模別の費用モデル
- 小規模オフィス(10名程度まで): 初期費用の総額は、20万円から50万円程度が一般的です。
- 中規模オフィス(11名〜50名程度): 初期費用の総額は50万円から150万円以上になることも珍しくありません。
【ポイント】 従来型を選ぶ際、メーカー以上に重要なのが「どの販売・工事会社から導入するか」です。信頼できる業者を見つけ、その業者が得意とする製品を導入することが、満足度の高い投資につながります。
クラウドPBXの価格と選定における重要注意点
クラウドPBXは初期費用を大幅に抑えられ、場所を選ばない働き方を実現できるため、近年導入する企業が急増しています。しかし、「サービス」であるがゆえの注意点があります。
料金体系の解説
クラウドPBXの料金は、主に「初期費用」「月額利用料」「オプション料金」「通話料」で構成されます。従業員の増減に合わせて月々のコストを柔軟に変えられるのが大きなメリットです。
契約前に必ず確認すべき4つのリスク
導入を成功させるには、価格だけでなく以下の4つのポイントを必ずベンダーに確認しましょう。
- 通話品質: 品質は利用するインターネット回線に大きく依存します。安定した通話品質を確保するには、自社のネット環境を見直し、高速な光回線を契約することが不可欠です。
- セキュリティ: ベンダーがどのようなセキュリティ対策(通信の暗号化、アクセス制限など)を講じているか、必ず確認しましょう。
- 電話番号の引き継ぎ: 「今使っている会社の代表番号を、そのまま使えるか」は非常に重要な問題です。契約前に、現在の番号が引き継がれるか明確な保証を得ることが絶対条件です。
- 緊急通報と停電時の対応: ほとんどのクラウドPBXは110番などの緊急通報に発信できません。また、停電時は社内の電話機は使えませんが、従業員のスマホアプリからは利用可能です。これは災害時の事業継続(BCP)対策として有効です。
導入費用を賢く抑える具体的戦略
ビジネスフォンの導入費用は、いくつかの戦略的な方法で賢く削減できます。
IT導入補助金の活用法
特にクラウドPBXは、ソフトウェアやクラウドサービスの利用料が対象となる「IT導入補助金」に非常に適しています。ベンダーが補助金の対象事業者かを確認することから始めましょう。
失敗しない相見積もりの進め方
複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」はコスト適正化の基本です。
- 要件を明確にする: 必要な電話機の台数や必須の機能などをリストアップします。
- 複数社に依頼する: 最低でも2〜3社以上に同じ条件を提示して依頼します。
- 見積書を精査する: 「工事費一式」のように内訳が不明瞭な見積もりは注意が必要です。価格だけでなく、担当者の対応やサポート体制も評価しましょう。
まとめ
ビジネスフォンの「価格」は、一つの数字で語れるものではありません。会社の戦略的な判断によって、その総コストは大きく変わります。
- 導入方法の選択: キャッシュフロー重視なら「リース」、長期的な信頼性を求めるなら「新品購入」、コスト最優先なら「中古購入」が基本です。
- 技術基盤の選択: 社内での管理と安定性を重視するなら「従来型」、働き方の柔軟性と拡張性を求めるなら「クラウドPBX」が候補となります。
これらの選択肢に絶対的な「正解」はありません。最適な答えは、企業の規模、予算、成長計画、働き方など、それぞれの会社が置かれた状況によってのみ決まります。
この記事が、複雑に見えるビジネスフォンの価格体系を解き明かし、皆様が自社にとって本当に価値のある投資判断を下すための一助となれば幸いです。
もし、具体的なプランニングや業者選びでお困りの際は、ぜひ私たち株式会社ドリームソリューションにご相談ください。専門家の視点から、貴社にとって最適なソリューションをご提案します。